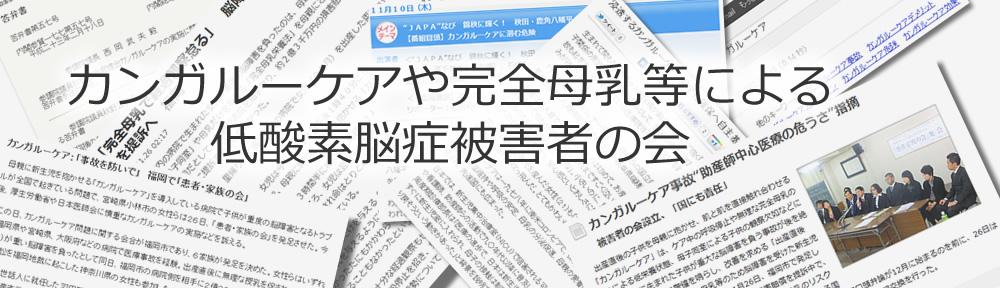医療系専門サイトに掲載された完全母乳に関する記事です。
完全母乳にこだわり過ぎると低血糖から脳障害になる恐れがあるという意見が掲載されています。
母乳をいかに与えるかは静かながらも熱を帯びた論争テーマとなってきた。
「産直後は基本的に母乳のみを与え、栄養補足は最小限」と今は学会は後押しする。
一方で「低血糖の懸念から母乳不足なら直ちに人工乳」の医師も。関連の訴訟も。賛否は?
補足は最小限か、母乳不足ならば直ちに人工乳の補給か
母乳基本的に母乳のみ
「産直後72時間の栄養方法がその後の完全母乳成功への鍵」と考える、さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック(宮城県)の堺武男氏。
「出産から退院するまでの72時間程度は、基本的に母乳のみで新生児に栄養を与えるのがよい。場合によっては糖水などを補足することもある」。宮城県さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック院長の堺武男氏はこう説明する。
学会も後押し
産直後の新生児に最優先で母乳だけを与えようと取り組む考え方は、日本小児科学会の委員会も後押しするものだ。学会の「母乳推進は小児科医の責務」と明記した2008年発表の「マニフェスト」に基づいて、2011年8月、学会の栄養委員会と新生児委員会は「小児科医と母乳育児推進」と題した報告を学会誌に掲載した。委員会は、母乳育児を積極的に推進する重要性を強調している。
母乳育児の一つの理想形は、新生児期の栄養の100%を母乳で賄う「完全母乳」の実現だろう。母乳栄養の定義について報告では、「直接搾乳や経管栄養などの投与方法に関わらず乳汁栄養のソースが母乳である」と位置付けている。母乳育児は栄養に占める母乳の割合によって大きく3種類に分かれており、生後にビタミン、ミネラル、薬を除いて母乳以外を与えないのは「完全母乳栄養」、母乳の割合が20%から80%は「混合栄養」、20%未満は「人工栄養」となっている。その上で、報告では、母乳の割合を「できるだけ多くするのが理想」と明記している。推進役として期待するのは小児科医で、「乳汁のソースができる限り母乳となるように小児科医が支援していく」と重要視している。
母乳育児を進める上で、大きく考え方が分かれるのは産直後の対応である。
産直後は母乳が出にくい場合も多い。「スタートダッシュが肝心」と産直後の授乳を重視して、その後の母乳の分泌を促進しようという考え方に立つ医師も多いだろう。「産直後は可能な限り母乳だけを与えたい」と考える医師の一人が堺氏だ。これまでも産直後は糖水や人工乳を不要と判断できる時はできる限り使わないよう心掛けてきた。
学会の報告でも母乳を最優先にする見方を明示している。
母乳育児を定着させる鍵となるのは「出生以後早期」と説明する。
重要なのは、まず産後30分以内に初回授乳すること。委員会では、「出生後早期にホルモン分泌が進むと、母乳の出は良くなる」と生理学の観点から解説している。母乳分泌を促す上で、新生児が乳頭を吸う刺激が重要になる。刺激は脳の下垂体に作用し、下垂体の前葉から乳汁分泌を促すプロラクチンが分泌される。プロラクチンは母性行動を起こさせる作用もある。さらに下垂体後葉から同様に乳汁分泌を促進するオキシトシンが分泌される。
委員会の報告には、新生児の出生後は2時間ほど温かいタオルにくるんで、母親が抱いて過ごすのが望ましいと記載。新生児が30分以内に母親の乳首を探し始めるので、吸えるようにすると勧めている。産直後の授乳には、母子が密着する利点も報告は指摘する。精神的なつながりが生まれるほか、母親の皮膚常在菌の移行による感染予防の効果もメリットとして挙がっている。
堺氏は、「健全な母子関係の確立にとっても、産直後の母乳育児は大きな意味を持つ」と考えている。
さらに、引き続き生後24時間も重要な時期となる。委員会の報告では、「生後24時間までの授乳回数が7回から8回以上あれば、母乳の分泌が良くなり、新生児黄疸の程度が軽減する」と重視する。いつでも授乳できるようにするため、生後は終日、母子同室が必須とも勧めている。
異種たんぱく質は避ける
「母乳をうまく出すために、産直後72時間くらいは基本的に糖水や人工乳の使用は控えるべきだろう。母乳だけを新生児に与えられるよう頑張ってほしい。新生児にとっても無理なく実践できると考えている」と堺氏は説明する。
新生児はグルコースを含む母乳からエネルギーを得るほか、糖新生や解糖、アセトン、アセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸といったケトン体の合成により自らエネルギーを作り出せる。母乳由来のエネルギー源が出生後に不足していても、新生児ならば十分にエネルギー源を自ら賄えると堺氏は考えている。
しかしながら、「いたずらに母乳以外は決して与えないことに固執すべきではなく、補足が必要な時もある」とも語る。体重減少率が10%となった場合、脱水が見られた場合、発熱がある場合など、新生児の状態を見ながら糖水を基本としてエネルギー減の補給も考慮に入れる。堺氏はほとんどの場合は母乳だけの栄養源で問題はないと考えている。「補足が必要な時も10mLから20mLと最少量とし、児の吸啜(きゅうてつ)意欲を損なうような量の補足は行わないことがその後の母乳育児の確立に重要である」(堺氏)。
人工乳の補給は異種たんぱく質であるため、アレルギーを引き起こす懸念を学会も指摘している。学会委員会の報告では、「新生児に異種たんぱく質を与えることにはアレルギーの問題もあることから、人工栄養を第一選択とすることには慎重でなければならない」と記述する。
母乳育児のメリットは報告済み。必要な栄養が過不足なく与えられる点、母子関係の確立を促す利益に加え、子供の発達への好影響、生活習慣病の予防、感染免疫力の向上、アレルギーの抑制などの効果もあるとの報告もある。堺氏は「目標は産科入院中に母乳育児が確立され、その後も多くの医師が母乳育児の継続を支援していただくこと」と望んでいる。
慎重母乳不足は速やかに人工乳
「生後72時間は体重減少が起こりやすく、状態によっては母乳栄養にこだわる必要はない」と話す山形大学小児科の早坂清氏。
「生後72時間までは、生理的に体重減少の程度が最大になる時期。母乳育児の実施は脱水や低血糖などに注意を払いながら慎重に行わなければならない」。山形大学小児科教授の早坂清氏はこう説明する。
脳障害のリスク
母乳育児を実践する点で早坂氏は全く異論を持っていないものの、産直後の母乳の不足時には「完全母乳栄養にこだわる必要はない」と考えている。「人工乳を与えるのを躊躇しない」という立場だ。
胎児期には胎盤を介して母体から栄養が補給される。出生後は母体からのエネルギー供給が絶たれるので、エネルギー源を得る必要がある。
糖分や脂肪を含む母乳からエネルギーを得るほか、身体に備蓄しているグリコーゲン、脂肪や筋肉を分解し、グルコースやケトン体を生成し、脳を筆頭として組織にエネルギー源を供給する。ケトン体はアセトン、アセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸を言う。低血糖に陥ったからといって、必ずしも新生児に脳をはじめとして障害が起きるわけではないのは、ケトン体といった代替エネルギーを活用できるからだ。
早坂氏は、「満期産であれば、大多数は母乳だけでも大丈夫だろう。しかし中には問題を抱えた新生児が存在している点を重く見るべきだ」と母乳栄養にこだわらない背景を話す。
問題は母乳摂取が不足した場合、低血糖に耐えられない新生児がいることだ。新生児の中には、糖新生やケトン体の生成、利用に問題のある代謝異常である場合のほか、糖新生に利用可能な基質の蓄積が少ない場合もある。この条件の下で母乳だけを栄養源にしようとすれば、エネルギー補給が足りなくなっても代替エネルギーの活用もままならず、低血糖に陥って障害を来たしてしまう。
「新生児の備蓄エネルギーは基本的に少ない。妊娠中の状況次第で母親から受け取るエネルギー量は異なり、備蓄エネルギーは一律ではない。また、新生児にかかるストレスにより新生児の消費エネルギーも異なる」と早坂氏は付け加える。
代謝異常や備蓄エネルギーの不足を見抜くのは難しい。早坂氏は、「問題が起きてから『たまたま運が悪かった』で済まされる問題ではない。安全育児を第一として、母乳が不足していると分かった時点で速やかに人工乳の補足を行うべきだろう」と話す。母乳育児を進める場合には、哺乳状況、体重変化、尿量の評価をし、全身状態を確認。人工乳の補給をためらわない。
「非常食」には頼らない
早坂氏は、「注意すべきなのは、生体にとってケトン体は非常食であり、『切り札』的な位置付けである点。ケトン体があるから、栄養が不足してもいいととらえるべきではないだろう」と話す。
低血糖によって脳障害が起こる懸念もある。早坂氏とともに診療に取り組む高橋信也氏は、完全母乳栄養で管理された正期産新生児で、低血糖によるけいれんが起こり、後に脳障害が残った事例を経験している。
出生直後から直接授乳を開始し、母親の哺乳力は良好と評価されたものの、3日目にけいれんが発生。10%の体重減少とBUN(血液尿素窒素)の上昇などから母乳不足による低血糖と判断できた。頭部MRIの画像から新生児低血糖に特徴的な異常信号を確認できた。
高橋氏はかねて生後早期の完全母乳栄養中に低血糖が生じ得ることに問題を感じてきた。「母乳にこだわった結果、脳障害に至れば、てんかんなどの発症にもつながりかねない」と見ている。早坂氏と同様に、産直後の完全母乳には消極的な立場を取る。
低血糖による脳障害を考える時、注意すべきは低血糖が持続する場合だ。「低血糖が短時間であれば、ケトン体といった代替エネルギーの利用で対応は可能かもしれない。また、けいれんなどの症状が出現しても、ブドウ糖を速やかに投与すれば後遺症は残さず回復する」(高橋氏)。しかし、低血糖が持続すると神経細胞に不可逆的な傷害を遺すことになる。高橋氏は、「新生児が低血糖に陥った時に、典型的な低血糖の症状である意識障害やけいれんだけではなく、無呼吸やチアノーゼといった非特異的な症状を呈する点は重要。過敏性が亢進し泣くこともある。低血糖の徴候は非特異的で気が付きにくい。医療者が危険を的確に察知し、予防的に対応する必要がある」と話す。
ICは重要
早坂氏らは「多くの医療者が新生児期の低血糖のリスクを重く見始めている」と考えている。「1980年代以降、2000年頃までには国内で治療介入が必要な低血糖の基準は、30mg/dLから40mg/dL以下の場合となっていた。今では50mg/dL以下の場合と高めに考えられるようになっている」(早坂氏)。新生児の血糖値の標準偏差に基づいて基準値を設定する考えから、どの新生児にも低血糖の症状が出ない水準以上に維持する見方に移ってきていると見る。
早坂氏は、「母乳の分泌には個人差がある。母乳栄養が大切か、新生児の安全が第一かの問題を考えるといい。育児で危険を冒す必要はあるのか。自分の子であれば、危険を冒す必要はないと考えるのが常識的だろう。母乳栄養では危険性についての警告が足りないと見受けられる」と語る。
早坂氏は、「母乳栄養のいいところばかり強調してはならない。新生児にとって栄養は医療行為と言っていい。母乳栄養を実施するならば、メリットとデメリットを親に正しく伝える必要がある。現状では、十分に説明していないケースが多いのではないだろうか。低血糖によって生涯にわたる問題が起きることもある。リスクが伴うからには、インフォームド・コンセントが必要だ」と強調する。